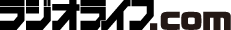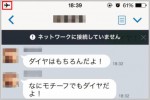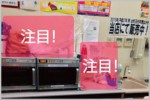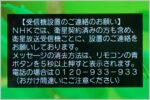戦闘訓練で領空侵犯機への警告に使用する周波数
エリアと呼ばれる訓練空域が、航空自衛隊の基地近くの洋上に設定されています。海岸からはその勇姿を見ることはできませんが、長いアンテナを使えば、交信をキャッチできるでしょう。訓練空域で実施される戦闘訓練にはGCIが使われます。模擬戦を行う部隊は、オフェンスやディフェンスなど分かれて、2対2や3対3などになります。

戦闘訓練で戦闘機同士の格闘戦を開始
戦闘訓練では、編隊ごとに別々のGCI波を使って戦闘機同士の格闘戦、ドッグファイトを開始。この際、戦闘を支援する地上迎撃管制官(GCIO)も訓練に参加します。
ディフェンス側の地上迎撃管制官は、GCI波で敵機の現在位置、速度、機動の状況を伝達して、迎撃するために有利なポジションへと味方機を誘導し戦闘を支援。双方の編隊長はGCI波で僚機と交信して連携し、攻撃するのです。
戦闘機パイロットは有名ですが、防空指令所などの地上要撃管制官にもTACネームが付けられているようです。TACネームは、GCI波の交信でコールサインのように使われます。
戦闘訓練の熱い様子を耳から感じ取る
戦闘訓練では、パイロットも熱くなっているので、カタカナ英語と日本語が入り交じる交信が多くなります。ボギー=敵機といった専門用語を覚えてしまえば、交信内容が理解できて、洋上で繰り広げられる戦闘訓練の熱い様子が耳から感じ取れることでしょう。
模擬戦以外にも領空侵犯機を設定し、国際法に準拠した法務執行の訓練も行います。進路変更を促す侵犯機前方への曳光弾を発射する信号警告射撃や、強制着陸の手順も含む訓練も行っているのです。
訓練時の領空侵犯機への警告は、国際緊急周波数である121.500MHzと243.000MHzは使用しません。訓練用のGCI波で代用するのです。全国の戦闘機部隊には、訓練用のGCI波のチャンネルが多数存在しますが、部隊内の訓練で使うのは数波のようです。(文/さとうひとし)
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- 市販のデジカメで超簡単に赤外線撮影する裏ワザ - 2026年2月5日
- 非常用トイレは排便袋と凝固剤を個別で用意する - 2026年2月4日
- 「ETC平日朝夕割引」は登録無料で最大50%引き - 2026年2月4日
- 高速道路の渋滞発生メカニズム「サグ」とは何? - 2026年2月4日
- iOS用スマートタグ3商品をAirTagと比較してみた - 2026年2月3日