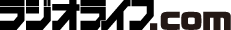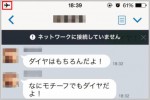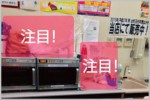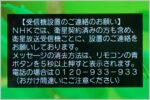航空路管制は「上下分離」で何が変わったのか?
航空路管制は、3つある航空交通管制部(以下、ACC)の広い管轄空域のすべてで、同じ周波数を使っているわけではありません。管轄空域を細かく分けたエリアごとに、周波数を割当てて別々の管制官が担当します。1人の管制官が担当できる最大機数が決められているため、混雑している空域ほど細分化されるのです。

航空路管制は上下分離で効率を上げる
この細分化された空域は「セクター」と呼ばれます。なお、セクターに入ることが可能な機数に達すると、航空機を別のセクターで待機させたり、空港を出発する時間を調整しているのです(EDCT:出発制御時刻)。
集中する航空機に対応するためにセクターをさらに分けていくと、今度は次から次へと周波数を変更することになり、パイロットにも負担になります。そのうえ、狭い空域では整流などに限界があり、逆に管制効率が落ちることになるのです。
そこで管制効率を上げることを目的として実施されたのが管制空域の「上下分離」です。高い巡航高度を飛ぶ航空機には、それほど多くの指示を出すことはありません。
航空路管制を高高度と低高度で分離
対して、低い高度で目的空港へ向かったり、出発空港から航空路へ上昇する航空機には頻繁に指示を出すことになります。動きが異なる多数の航空機を1人の管制官が担当するよりも、高高度と低高度を別の空域として管制するのが上下分離の概要です。
高高度帯は全国を一括して福岡ACCが担当し、低高度帯は西日本が神戸ACC、東日本を東京ACCが担当。高度の境界はFL335(FL=フライトレベルで33,500フィート/10,210m)で、セクターによってはさらに低高度帯が2分割されているところもあります。
FL335に達しない近距離の路線や低高度を飛ぶ小型機の場合は、高高度セクターにはコンタクトせず、低高度セクターのまま運航することもあるのです。
The following two tabs change content below.


ラジオライフ編集部
ラジオライフ編集部 : 三才ブックス
モノ・コトのカラクリを解明する月刊誌『ラジオライフ』は、ディープな情報を追求するアキバ系電脳マガジンです。
■編集部ブログはこちら→https://www.sansaibooks.co.jp/category/rl
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- 終了間近!高速を一度降りても同料金ETCサービス - 2026年2月22日
- 商業施設や飲食店のフリーWi-Fi速度を調査した - 2026年2月21日
- NHK受信契約が「義務化」されたのはいつから? - 2026年2月21日
- ETCカードが盗難に遭ったら最初にすべき手続き - 2026年2月21日
- YouTubeアプリ改造クラアイントには法的リスク - 2026年2月20日
この記事にコメントする
あわせて読みたい記事
関連する記事は見当たりません。