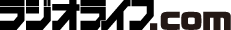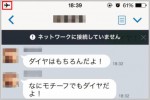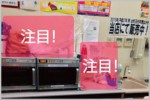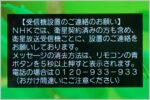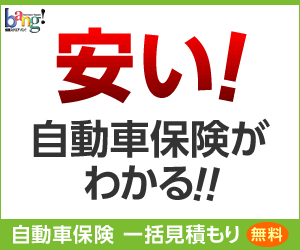高速道路で渋滞が発生する原因「サグ」とは何?
ラジオなどで流れる高速道路の道路交通情報では、毎日のように決まった地点を先頭にした渋滞情報が流れています。これは、単に走っている車が多いだけでなく、道の構造上、渋滞を引き起こしやすくなっているポイントがあるからです。高速道路の渋滞ポイント「サグ」について、詳しく見ていきましょう。

サグでは勾配が切り替わって渋滞発生
高速道路で渋滞がおきやすいと場所といえば、インターチェンジ(IC)やジャンクション(JST)などの合流ポイントです。車線が減る場所も、合流があるのでこれに含まれます。合流ポイントでは自動車のスピードが下がりやすく、それをきっかけに渋滞が始まるのです。
ところが、合流ポイントでもないのに、なぜか渋滞が発生しやすい場所があります。それが「サグ」と呼ばれる渋滞発生ポイントです。サグとは、道の勾配が下りから水平や上りに切り替わっている場所になります。
サグでは、勾配が切り替わって知らないうちにスピードが落ちてしまう自動車が増え、後続車がブレーキを踏む回数が増加。これをきっかけに渋滞が始まることが多いのです。サグとは、下り坂から上り坂にさしかかる凹部のこと。英語の「sag」の「たわみ」という意味に由来しています。
国土交通省が今年発表した2019年の渋滞ランキングでは、ワースト1位が東名高速上り海老名JCT~横浜町田ICでした。じつは、途中の大和バス停付近がサグになっています。2位は中央道の上り調布IC~高井戸ICですが、この間の深大寺バス停近くにサグがあり、渋滞が起きやすくなっているのです。
サグで渋滞の原因にならない走り方
このほか、3位の東名高速上り川崎IC~東京ICは料金所によるものですが、4位にまたサグの東名高速下り横浜町田IC~海老名JCTが続きます。このように、渋滞を引き起こす原因にサグが絡んでいることは多いのです。
ちなみに、渋滞が起きると長く伸びることで有名な中央道上り小仏トンネル付近は、トンネル内のサグに加えてトンネル入口での減速が組み合わさって、大きな渋滞の原因になっています。
こうしたサグのような渋滞ポイントで、自分が渋滞の原因にならないためには、常に走行中はスピードを気を付けることが大切。勾配変化でスピードが落ちる前にアクセルを踏めば、減速は少なくてすみます。そして、合流部では早めに車線を変更。急な車線変更は、後続車の急ブレーキにつながり、渋滞を引き起こす原因になります。
もう一つ大切なことは、適切な車間距離をとることです。車間距離が短いと急ブレーキを踏むことが増え、これが渋滞の原因につながります。適正な車間距離は時速100km/hであれば100m以上といわれ、渋滞だけでなく追突事故を防ぐためにも、車間距離には注意したいところです。
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- チープシチズンの中心ブランド「Q&Q」何の略? - 2026年1月27日
- 長距離フェリーのNHK受信料「特別契約」だった - 2026年1月27日
- 盗聴器の発見場所で2位はホテルで1位はどこだ? - 2026年1月27日
- 「情熱価格」ほかドンキのプライベートブランド - 2026年1月26日
- キャンピングカー高速代をETCゲートどう計算? - 2026年1月26日