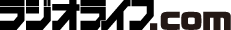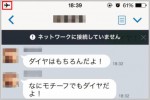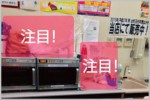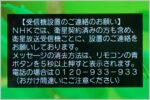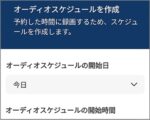誘導無線は無線局ではなく高周波利用施設だった
私鉄の列車無線では主に150MHz帯を使いますが、地下鉄では100~275kHzの長波を使用する「誘導無線」を導入しているところがあります。VHF帯やUHF帯は、トンネル内に効率よく電波を届けるには不向き。線路に平行して電線を敷設し長波の電波を乗せ、車両のアンテナと電磁誘導の原理で通話します。

誘導無線の受信は専用アンテナが必要
誘導無線は、線路に平行して「誘導線」と呼ばれる電線を敷設し長波の電波を乗せ、車両のアンテナと電磁誘導の原理で通話。これなら、トンネル内であっても誘導線があれば安定した通話が可能になります。
誘導無線は、電波法では「無線局」ではなく「高周波利用施設」の扱い。そのため、電波は微弱で線路から数メートル離れただけで受信できなくなります。
また、受信機の下限である100kHzに近いため感度も悪く、波長が長いので付属アンテナでは対応できず、専用のアンテナが必要。毛色が違ってハードルが高いものの、AMラジオ放送用のバーアンテナを内蔵した受信機のうち、アルインコ製は誘導無線の周波数帯にも使うことができます。
誘導無線は地下鉄だけでなく私鉄も導入
東京地下鉄(東京メトロ)や札幌市交通局など一部の誘導無線では、指令側周波数で通話がない時でも常に無変調を送信。裏を返すと、無変調が受信できれば通話を聞くことが可能であると判断できます。
誘導無線は地下鉄だけでなく、地下鉄と直通し運行が一体化している私鉄にも導入。具体的には、北大阪急行や近鉄けいはんな線などが該当します。また、ワンマン運転の地下鉄では、誘導無線よりもデータ通信に適した150MHz帯を使用する路線も存在します。
線路沿いに、電波を発射するアンテナと電波を運ぶ同軸ケーブル両方の機能を兼ね備えた漏洩同軸ケーブル(LCX)を敷設することで、安定した通話を実現しています。トンネル内や駅の天井近くにある、黒くて太いケーブルがLCXです。(文/おだQ司令)
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- スマートウォッチ型ICレコーダーは操作性が抜群 - 2026年2月6日
- オービスのスピード違反はレンタカーは対象外? - 2026年2月6日
- スマホが盗聴器に早変わりするレコーダーアプリ - 2026年2月6日
- Androidスマホ用キーロガーが記録するスゴイ中身 - 2026年2月5日
- レンタカーでもETCのポイント還元を受ける方法 - 2026年2月5日