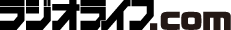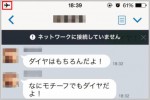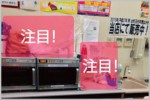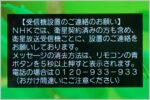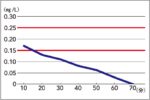消防士の緊張感に満ちた交信が聞こえる署活系
2016年5月31日がアナログ消防無線の使用期限です。しかし、すべての消防無線がデジタル無線になるわけではありません。デジタル無線の対象は、140~150MHz帯に存在する市町村波、県内共通波、全国共通波、救急波、消防団波。消防士の現場の声が聞こえる署活系はアナログ波のままです。

消防士同士が連絡を取る署活系
これは140~150MHz帯の再編成のため、この帯域にある割当てを260~270MHz帯へ引っ越しさせてデジタル無線化。同じ帯域に割当てがある防災行政無線移動系も、同様に260~270MHz帯への変波&デジタル無線化を開始しています。
すでに消防無線の140~150MHz帯の大移動が始まっています。しかし、これ以外の帯域にある消防無線はデジタル無線化の対象外ということになり、アナログ波での運用が継続されるのです。
デジタル無線の対象外の筆頭が、466MHz帯の署外活動波、“署活波”や“署活系”と呼ばれる無線。消防無線の主力である市町村波が消防本部と消防車を結ぶ基幹系なのに対して、署活系は活動現場で消防士同士が連絡を取るための無線です。
消防士の緊張感に満ちた交信
署活系は17波ありますが、消防本部の規模によって割り当てられる周波数が決められます。消防本部に消防署が多数あれば、割当て周波数も多くなります。消防士が多数集まる現場では、隊員間の連絡に署活系が必要になってくるからです。
署活系は活動現場にいる消防士同士の通信系なので、送信出力1Wのハンディ無線機での運用が基本。短めのアンテナも貧弱ですから、電波は遠くまでは飛びません。受信するためには活動現場の直近に行かないと難しいでしょう。
出力が高く、基地局の大きなアンテナから送信される市町村波のように、家で受信できるようなものではありません。署活系は積極的に街に出て行くか、自宅に外部アンテナを設置して受信します。署活系を受診すれば、活動現場で行われる消防士の緊張感に満ちた交信が聞こえてくるでしょう。(文/さとうひとし)
■「消防士」おすすめ記事
消防無線は組織の運営が違っても運用方法は同じ
消防無線の周波数は市町村波と共通波をスキャン
消防無線の周波数は「市町村波」が基本中の基本
消防ヘリの無線「カンパニーラジオ」って何?
防災訓練の消防防災ヘリが使用する周波数とは
デジタル無線の導入で聞ける消防無線が急増中
消防無線はアナログ波の署活系でデジタルを聞く
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- 渋滞情報を共有する無料カーナビアプリ便利機能 - 2025年7月15日
- スマホで確認できる?スピード違反の取締り情報 - 2025年7月15日
- ガソリン代を1円でも安くする節約テクニック5つ - 2025年7月15日
- ビール350ml缶なら20分後には酒気帯び以下に? - 2025年7月14日
- オービスの速度違反で警察の呼び出しは何日後? - 2025年7月14日