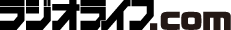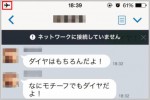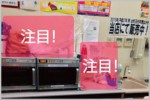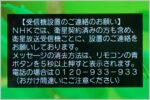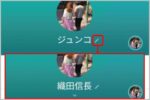東芝が東京芝浦電気だったころの小型BCLラジオ
1970年代後半、BCLブームが過熱して各メーカーからBCLラジオの新機種が次々に登場するようになりました。機能・性能アップと引き替えに価格も上昇し、ついに中心価格は3万円前後となったのです。そんな中、1976年11月に東京芝浦電気から登場したのが「トライエックス(TRYX)1700」こと「RP-1700F」です。

RP-1700Fはコスパに優れたBCLラジオ
東京芝浦電気のBCLラジオ「RP-1700F」は、比較的小さなボディで18,500円という手頃な価格ながら、他社の上級モデルと同様に短波帯は28MHzまでカバー(SW1:3.8~12MHz/SW2:15~28MHz)。
そして、マーカー発振器と円盤状の大型スプレッドダイヤルの装備で5kHzまでの周波数直読が可能となるという、コストパフォーマンスに優れたモデルでした。
ただし、RP-1700Fはシングルスーパーヘテロダイン方式で、イメージ信号が大きく出る傾向にあり、本物のマーカー信号とイメージ受信したマーカー信号を区別するのには慣れが必要だったのです。特にSW2バンドの15~28MHzはイメージ受信が強く出るためマーカーの使用には熟練を要しました。
RP-1700Fにモールスの送信練習機能
また、東京芝浦電気のBCLラジオに採用されたマーカー発振器の多くは、コイルとコンデンサを組み合わせたLC発振回路で、温度変化による周波数安定度がいま一つという難点もあったのです。
そこでRP-1700Fは、スプレッドダイヤルの右下に「MARKER ADJ」と記された調整孔を設け、「JJY」(短波帯の標準電波)を聞きながら、この穴にドライバーを入れてマーカー周波数を校正できるように改善されたのです。
また、アマチュア無線のSSBモードやモールス通信を聞く場合に必須のBFO(Beat Frequency Oscillator/うなり発振器)は組み込まれておらず、隣接周波数からの混信除去に効果があるフィルターの帯域可変機能も設けられませんでした。
代わりにオマケ機能として、モールス符号の送信練習機能(照明兼用のMORSE CODE TRAININGボタンを押すとトーン信号が出る)が設けられていました。
■「ラジオ」おすすめ記事
ラジオおすすめの1台はソニーのICF-M780N
BCLラジオのおすすめはソニーを超えたPL-880
InterFMが89.7MHzへ周波数を変更した理由とは
ソニーのラジオ新定番「ICF-M780N」は感度良好
AFNラジオ(FENラジオ)はアプリで周波数不明でも聴ける
radikoタイムフリー制限の時間をリセットする裏ワザ
radikoエリアフリー判定を無料で地域外で聞く裏ワザ
radikoがなぜ3時間以上はタイムフリーで聴けないのか?
radiko位置情報を偽装して地域外で聞く方法とは
radikoの音質はFMラジオと比べてどちらがよい?
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- 職務質問で慎重に対応するべき警察官の見分け方 - 2025年7月1日
- 運運転免許証番号で紛失などで再発行したかわかる - 2025年7月1日
- 災害時はラジオより「防災テレビ」という選択肢 - 2025年6月30日
- 自転車の並走は交通違反で青キップの反則金3千円 - 2025年6月30日
- LINEの友だちは名前変更しても相手には通知なし - 2025年6月30日