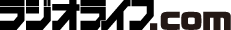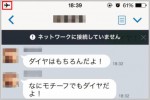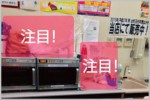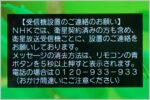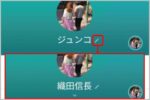ミニコンポにもなる大型ラジカセの使い道とは?
1980年代に入るとラジカセはワンピースボディから、スピーカーが分離する3ピース機種が新たに登場し始めます。また、この時代はラジカセの大型化と小型化が同時に進んだ頃で、ラジカセの歴史の中で一つの頂点が築かれた時期なのです。レイアウトを選ばないラジカセを超えた大型マシンの東芝「RT-S98」を見ていきましょう。

東芝のテクノロジーの集大成ラジカセ
小型化の頂点が、三洋電機の“おしゃれなテレコU4”とすると、大型化の頂点は紛れもなく東芝のラジカセ「RT-S98」になります。
大型機種として有名なシャープのサーチャーシリーズもありますが、RT-S98は当時の東芝が持つオーディオ系のテクノロジーを集大成したハイテクラジカセで、「adres」を搭載し透明感のある音質を実現しています。
スピーカーが分離できるのでミニコンポスタイルで聞くと、さらに迫力のある音が楽しめるのです。ちなみにスピーカーはウレタンエッジを採用し、繊細な音も再現できるポテンシャルを持っています。
ホームカラオケの機材に大型ラジカセ
しかし高性能であるがゆえ、RT-S98の価格は10万円オーバーと高額で、入手できたのはお父さんたちでしょう。1980年代初頭はホームカラオケがブームになり、そのメイン機材として多機能の大型ラジカセが重宝された時代でした。
RT-S98の主な機能は、同時録音可能ダブルカセット、アドレス・ノイズリダクション、スピーカー分離、ESBSコントロール(重低音)、9曲飛越し選曲(MQJS)、ダブルミキシングとなります。
受信周波数はAMラジオ放送(525~1605kHz)、FMラジオ放送(76.0~108.0MHz)で、出力はステレオ/最大30W(15W+15W)です。電源は単1形乾電池×10本、AC100Vで、サイズ/重さは740W×379H×180D㎜/15kg。1982年に発売された当時の価格は125,000円です。
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- ETCカードは限度額オーバーでそのまま使える? - 2025年7月3日
- 1万円を切るヘルメット装着の自転車用ドラレコ - 2025年7月2日
- 2台1組の白バイは新人研修中でじつは注意が必要 - 2025年7月2日
- 値下げしたNHK受信料より沖縄はもっと安かった - 2025年7月2日
- TVerで「見逃し」を防止するため活用したい機能 - 2025年7月1日
この記事にコメントする
あわせて読みたい記事

ラジカセにリモコンを世界初で搭載した東芝の機種は?

東芝のラジカセ「ACTUS」ブランドでも光る存在

東芝ラジカセ搭載の独自ノイズリダクションとは

パラボラが取り付けられる東芝のラジカセとは?
オススメ記事

2021年10月、ついに「モザイク破壊」に関する事件で逮捕者が出ました。京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、人工知能(AI)技術を悪用してアダルト動画(AV)のモザイクを除去したように改変し[…続きを読む]

モザイク処理は、特定部分の色の平均情報を元に解像度を下げるという非可逆変換なので「モザイク除去」は理論上は不可能です。しかし、これまで数々の「モザイク除去機」が登場してきました。モザイク除去は[…続きを読む]

圧倒的ユーザー数を誇るLINEは当然、秘密の連絡にも使われます。LINEの会話は探偵が重点調査対象とするものの1つです。そこで、探偵がLINEの会話を盗み見する盗聴&盗撮テクニックを見ていくと[…続きを読む]

盗聴器といえば、自宅や会社など目的の場所に直接仕掛ける電波式盗聴器が主流でした。しかし、スマホ、タブレットPCなどのモバイル機器が普及した現在、それらの端末を利用した「盗聴器アプリ」が急増して[…続きを読む]

おもちゃの缶詰は、森永製菓「チョコボール」の当たりである“銀のエンゼル”を5枚集めるともらえる景品。このおもちゃの缶詰をもらうために、チョコボール銀のエンゼルの当たり確率と見分け方を紹介しまし[…続きを読む]