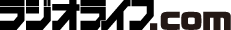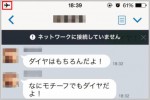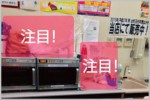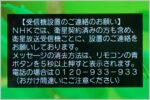デジタル化する鉄道無線でアナログが残るのは?
鉄道無線、特に列車無線はデジタル化が進行中。山陽新幹線以外の新幹線や、在来線でもJR東日本では地方を含めた多くの路線が、JR西日本でも京阪神エリアの大半で列車無線がデジタル化しています。関東では大手私鉄もデジタル化が始まり、聞けない無線になってきているのです。しかし、諦めるのは早過ぎます。

鉄道無線にまだまだアナログ無線使用
中京・関西・九州の大手私鉄や全国に多数存在するローカル私鉄の大半は、鉄道無線にまだまだアナログ無線を使用するからです。受信できる地域差が大きい無線ですが、私鉄のアナログ鉄道無線を紹介しましょう。
中京・関西・九州の大手私鉄の大きな特徴は、鉄道無線システムに大ゾーン方式を採用していることです。大ゾーン方式というのは、鉄道無線の基地局を山上や建物の屋上に設置して、25~50Wといった高出力で送信。全線を1つの基地局でカバーする方式です。
これとは逆のシステムが小ゾーン方式で、沿線に1~5W程度の指向性を持たせた基地局を多数設置して沿線を細かくカバー。JRや関東の大手私鉄の鉄道無線が採用しています。
鉄道無線が20km以上離れて聞こえる
どちらにも、メリットとデメリットがあるのですが、大ゾーン方式の鉄道無線は受信する側にとっては有利です。高所から強い電波を出しているため、かなりの広範囲に届きます。このため、沿線から遠く離れていても十分に受信できるのです。
例えば、阪急京都本線の沿線でも、20km以上離れた近鉄奈良線の鉄道無線がバッチリ聞こえてきます。関西は、大手私鉄が縦横無尽に路線を延ばしているので、鉄道無線を聞く際は各路線の周波数を貪欲にスキャンして下さい。
ただし、最近は少し傾向が変化。大ゾーン方式は高出力の1局を基地局としているため、故障や災害で機能しなくなると鉄道無線が全く使えなくなってしまい、全列車の運行を停止せざるをえません。
鉄道無線は本数の多い路線に通話あり
このリスク対策を考える鉄道会社が出始めているのです。そこで考案されたのが中ゾーン方式の鉄道無線。このシステムは、大ゾーン方式の基地局を分割配置したもので、5~10W程度の基地局を沿線に複数設置して全線をカバーするもの。1局集中の大ゾーン方式のリスクを分散します。
中ゾーン方式の鉄道無線の電波は、大ゾーン方式のようには飛びませんが、小ゾーン方式よりは依然飛びますので、沿線から少々離れても十分に聞けます。
受信エリアの広い私鉄の鉄道無線であっても、平常運行であれば交信はそう多くはありません。しかし、おもしろ無線界の格言に「人の集まるところに無線あり」というものがあります。これを鉄道無線に当てはめるならば、「乗客・運行本数の多い路線に通話あり」です。(写真・文/神戸の受信マニア)
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- カスハラ対応でスマホ通話録音に便利なアイテム - 2025年7月4日
- 自転車にも導入される「青キップ制度」対象年齢 - 2025年7月3日
- 運転免許に累積している点数リセットする裏ワザ - 2025年7月3日
- ETCカードは限度額オーバーでそのまま使える? - 2025年7月3日
- 1万円を切るヘルメット装着の自転車用ドラレコ - 2025年7月2日
この記事にコメントする
あわせて読みたい記事

ブルーの展示飛行の様子を基地外周から把握する

聞けるマスコミ無線「VHF帯放送連絡波」周波数

まだアナログで聞けるマスコミ無線は何がある?

首都高の渋滞と迂回路の指示が聞こえるバス無線
オススメ記事

2021年10月、ついに「モザイク破壊」に関する事件で逮捕者が出ました。京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、人工知能(AI)技術を悪用してアダルト動画(AV)のモザイクを除去したように改変し[…続きを読む]

モザイク処理は、特定部分の色の平均情報を元に解像度を下げるという非可逆変換なので「モザイク除去」は理論上は不可能です。しかし、これまで数々の「モザイク除去機」が登場してきました。モザイク除去は[…続きを読む]

圧倒的ユーザー数を誇るLINEは当然、秘密の連絡にも使われます。LINEの会話は探偵が重点調査対象とするものの1つです。そこで、探偵がLINEの会話を盗み見する盗聴&盗撮テクニックを見ていくと[…続きを読む]

盗聴器といえば、自宅や会社など目的の場所に直接仕掛ける電波式盗聴器が主流でした。しかし、スマホ、タブレットPCなどのモバイル機器が普及した現在、それらの端末を利用した「盗聴器アプリ」が急増して[…続きを読む]

おもちゃの缶詰は、森永製菓「チョコボール」の当たりである“銀のエンゼル”を5枚集めるともらえる景品。このおもちゃの缶詰をもらうために、チョコボール銀のエンゼルの当たり確率と見分け方を紹介しまし[…続きを読む]