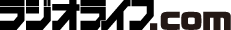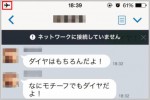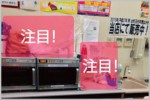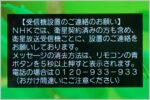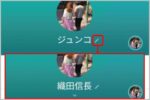SITは警察の捜査一課特殊班の略称で由来はローマ字
SITの正式名称は「刑事部捜査一課特殊犯捜査班」で、各警察本部の刑事部に設けられた捜査一課の一部署です。捜査一課特殊班の主な任務は誘拐事件などの捜査と人質救出になります。警察が捜査一課特殊班を設立したのは1964年。きっかけは前年に東京都台東区で起きた「吉展ちゃん誘拐事件」です。

SITは警察本部で呼び名が違う場合
この事件で警視庁の捜査官は、身代金を奪われて犯人を取り逃がした上に、吉展ちゃんの命をも奪われるという大失態を犯してしまいました。それを教訓に、警察の誘拐捜査の専門班として創設されたのです。
警察の捜査一課特殊班「SIT」の略称の由来は少し変わっていて、「Sousa Ikka Tokusyuhan」。つまり「捜査一課特殊班」のローマ字表記の頭文字からきているといわれています。
しかし、捜査一課特殊班の部隊腕章には「Special InvestigationTeam」の文字が表記。これは在外公館勤務経験者の捜査一課管理官が、SITを「Special InvestigationTeam」の略称と解釈してしまい、それが公式化したとの説もあります。
この捜査一課特殊班の呼び名は警察本部によって、違う場合もあります。埼玉県警は「STS」で「Special Tactical Section」の略。千葉県警は「ART」で「Assault and Rescue Team」の略。神奈川県警は「SIS」で「Special Investigation Squad」、大阪府警「MAAT」で「Martial Arts Attack Team」です。
SITの警察官は人質の安全を確保
警察の捜査一課特殊班「SIT」の任務はミスを犯せば人質の命だけでなく、自分も危険にさらしてしまうため、訓練は最悪の事態を想定して行われているといいます。しかし、捜査一課特殊班の本来の目的は、人質の安全を確保して救出することと犯人の逮捕。捜査一課特殊班にとって、強行突入は最終手段になります。
それゆえ、捜査一課特殊班は通信傍受や逆探知を駆使して情報を入手しつつ、犯人と交渉、説得するという役目も重要。その説得を専門にするスペシャリストが「ネゴシエーター」と呼ばれる交渉役です。
2002年に起きた福岡県二丈町の民家立てこもり事件では、犯人との交渉が長引き、人質になっていた9歳の女児が刺殺されてしまいました。その反省を踏まえ、警察庁が全国の警察にネゴシエーターを置くことを決定。
捜査員の中から選抜された警察官たちが警察大学校で海外の交渉術や心理学を学び、そのテクニックを身に付けたといわれています。
■「捜査一課」おすすめ記事
鑑識の仕事!立場は捜査一課の刑事と同じだった
■「特殊部隊」おすすめ記事
銃器対策部隊は全国の警察本部に配置されている
警察の特殊部隊「SAT」は高性能の銃器を装備
■「警察」おすすめ記事
駐車禁止を警察が取り締まれない「植え込み」
駐禁をとられても警察に出頭する必要はない
駐車禁止違反は苦手!?注意だけの警察官が増加中
警察用語では拳銃はチャカではなく腰道具と呼ぶ
警察用語でやどは留置場で別荘は刑務所のこと
公安警察はデモや集会に私服で必ず張っている
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- 職務質問で慎重に対応するべき警察官の見分け方 - 2025年7月1日
- 運運転免許証番号で紛失などで再発行したかわかる - 2025年7月1日
- 災害時はラジオより「防災テレビ」という選択肢 - 2025年6月30日
- 自転車の並走は交通違反で青キップの反則金3千円 - 2025年6月30日
- LINEの友だちは名前変更しても相手には通知なし - 2025年6月30日
この記事にコメントする
あわせて読みたい記事

捜査一課が使う「げんじょう」「げんば」の違い

花形部署と思われがち「捜査一課」の仕事と給料

警視庁捜査一課の赤バッジ「S1S mpd」意味は?

警察で刑事が所属する捜査一課は何課まである?
オススメ記事

2021年10月、ついに「モザイク破壊」に関する事件で逮捕者が出ました。京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、人工知能(AI)技術を悪用してアダルト動画(AV)のモザイクを除去したように改変し[…続きを読む]

モザイク処理は、特定部分の色の平均情報を元に解像度を下げるという非可逆変換なので「モザイク除去」は理論上は不可能です。しかし、これまで数々の「モザイク除去機」が登場してきました。モザイク除去は[…続きを読む]

圧倒的ユーザー数を誇るLINEは当然、秘密の連絡にも使われます。LINEの会話は探偵が重点調査対象とするものの1つです。そこで、探偵がLINEの会話を盗み見する盗聴&盗撮テクニックを見ていくと[…続きを読む]

盗聴器といえば、自宅や会社など目的の場所に直接仕掛ける電波式盗聴器が主流でした。しかし、スマホ、タブレットPCなどのモバイル機器が普及した現在、それらの端末を利用した「盗聴器アプリ」が急増して[…続きを読む]

おもちゃの缶詰は、森永製菓「チョコボール」の当たりである“銀のエンゼル”を5枚集めるともらえる景品。このおもちゃの缶詰をもらうために、チョコボール銀のエンゼルの当たり確率と見分け方を紹介しまし[…続きを読む]