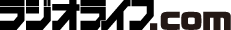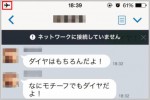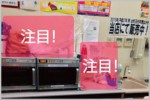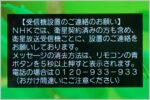東京消防庁の無線だけ互換性ないTDMA方式の理由
2016年5月31日の夜に、アナログ波による交信を終えた東京消防庁の無線。以後、東京消防庁はデジタル消防無線の運用に完全移行して、市販の受信機では通話内容を聞くことはできなくなりました。東京消防庁の無線で特筆すべきはデジタルの方式です。他の消防機関はすべてSCPC方式を採用しているのですが、東京消防庁の無線だけが互換性の無いTDMA方式になっています。

東京消防庁の無線は方面波で運用
日本の消防制度は「自治体消防」で、市町村が独自に消防本部を設置して地域を管轄する方式です。財源的に厳しい自治体では周辺の自治体と共同で「組合消防」を組織しています。
その中にあって異例なのが、東京消防庁。独自消防を組織している稲城市と島嶼部を除いた都内全域を管轄しているのです。
昼間の人口が1,600万人にも達する東京。火災だけではなく、救助や救急要請も格段に多くなります。そこを管轄する東京消防庁は、世界にも類を見ない大組織。東京消防庁の消防署は81署あり、分署や出張所含めると合計で292か所も存在するのです。
東京消防庁は管轄内を10個の方面に分けて運用しています。通信を担う消防無線は各方面に方面波が2波、これが10方面分あり20波で、統制波3波と主運用波1波を加えた24波が最低でも必要です。
東京消防庁の無線はTDMA方式採用
さらに東京消防庁は救急波・受令波・携帯共通波も運用しており、不感地帯用の中継波も必要。東京消防庁は少なくとも50波以上の周波数を運用していることになるのです。270MHz帯に割当てられたデジタル消防無線の周波数は320波あるのですが、東京消防庁が50波以上を占有してしまうと、隣県の消防本部の割当てに影響が出てきます。
そこで東京消防庁の消防無線は、25kHz幅の1波に4チャンネルが入るTDMA方式を採用し、消防と救急業務に使用しているのです。なお、東京消防庁で特殊運用される部隊や受令波、全国共通の統制波と主運用波を全国標準のSCPC方式に分けて運用していると推測されます。
なお、東京消防庁も県境などの事案では相互応援協定により、他県の消防本部との連携が必要です。このため、東京消防庁は消防車にSCPC方式の無線機を搭載して通信しています。
■「消防無線」おすすめ記事
消防無線は組織の運営が違っても運用方法は同じ
消防無線の周波数は市町村波と共通波をスキャン
消防無線の周波数は「市町村波」が基本中の基本
消防ヘリの無線「カンパニーラジオ」って何?
防災訓練の消防防災ヘリが使用する周波数とは
デジタル無線の導入で聞ける消防無線が急増中
現場の隊員間の通話が聞ける消防無線の魅力とは
ラジオライフ編集部
最新記事 by ラジオライフ編集部 (全て見る)
- TVerに無料登録すると開放される限定機能とは? - 2025年7月5日
- 警察の特殊部隊「SAT」初めて表舞台に出た事件 - 2025年7月5日
- 河川の氾濫で地元の有力情報が入る防災無線とは - 2025年7月5日
- マイナ免許証は1枚持ちと2枚持ちでどっち便利? - 2025年7月4日
- ネズミ捕り現認係が潜むのは道路脇のほかどこ? - 2025年7月4日
この記事にコメントする
あわせて読みたい記事

ブルーの展示飛行の様子を基地外周から把握する

聞けるマスコミ無線「VHF帯放送連絡波」周波数

まだアナログで聞けるマスコミ無線は何がある?

首都高の渋滞と迂回路の指示が聞こえるバス無線
オススメ記事

2021年10月、ついに「モザイク破壊」に関する事件で逮捕者が出ました。京都府警サイバー犯罪対策課と右京署は、人工知能(AI)技術を悪用してアダルト動画(AV)のモザイクを除去したように改変し[…続きを読む]

モザイク処理は、特定部分の色の平均情報を元に解像度を下げるという非可逆変換なので「モザイク除去」は理論上は不可能です。しかし、これまで数々の「モザイク除去機」が登場してきました。モザイク除去は[…続きを読む]

圧倒的ユーザー数を誇るLINEは当然、秘密の連絡にも使われます。LINEの会話は探偵が重点調査対象とするものの1つです。そこで、探偵がLINEの会話を盗み見する盗聴&盗撮テクニックを見ていくと[…続きを読む]

盗聴器といえば、自宅や会社など目的の場所に直接仕掛ける電波式盗聴器が主流でした。しかし、スマホ、タブレットPCなどのモバイル機器が普及した現在、それらの端末を利用した「盗聴器アプリ」が急増して[…続きを読む]

おもちゃの缶詰は、森永製菓「チョコボール」の当たりである“銀のエンゼル”を5枚集めるともらえる景品。このおもちゃの缶詰をもらうために、チョコボール銀のエンゼルの当たり確率と見分け方を紹介しまし[…続きを読む]